ベース弾きはコントラCの夢を見るか?
演奏会本番前、楽屋脇の廊下のソファで、エキストラにやってきたチェロ弾きの音大生が2人、煙草を吸いながら話している。
「ベースもさぁ、運命の2楽章の、あのCなんていいよなぁ」
向かいのソファでぐったりとしていたベース弾きは思わず耳をそばだてる。そう、コントラバスは普通たんなる縁の下の力持ちで、あまり活躍する場面はない。いや、活躍はするのだが、音が低いのでゴソゴソしているなぁという感じを与えるだけで、バイオリンやチェロのようにはったりの効く名旋律を朗々と奏でるチャンスには恵まれない。
旋律楽器の奏者は、だから大抵はあまりベースのことをよく知らないようだ。まあこれは旋律楽器奏者に限った話ではなく、ベース弾きがどんなところに生き甲斐を感じるのかなどということは、関知していないのが普通である。そんな中で、この音大生のつぶやきはなかなかポイントをついていた。いい音楽を知っているなと思わせるひとことだ。
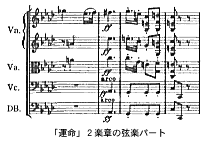 ベートーベンの交響曲第5番の2楽章には、これぞコントラバスという最低音のCが極めて効果的に用いられている。変イ長調の優雅な主題が示されたあと堂々とした変奏に入っていくのだが、その直前にいったんフォルテシモでハ長調の終止が現れる(30-31小節)。全合奏の第1拍に続いてチェロとバスだけが奏するこの2拍目の終止音が、実にしびれるのだ。たった1つの音符に過ぎないのに、これを弾くときバス奏者は「ああ、この楽器を選んで良かった」と思う。大袈裟にいえば、コントラCに宇宙を感じるのである。
ベートーベンの交響曲第5番の2楽章には、これぞコントラバスという最低音のCが極めて効果的に用いられている。変イ長調の優雅な主題が示されたあと堂々とした変奏に入っていくのだが、その直前にいったんフォルテシモでハ長調の終止が現れる(30-31小節)。全合奏の第1拍に続いてチェロとバスだけが奏するこの2拍目の終止音が、実にしびれるのだ。たった1つの音符に過ぎないのに、これを弾くときバス奏者は「ああ、この楽器を選んで良かった」と思う。大袈裟にいえば、コントラCに宇宙を感じるのである。
最低音のCは、近代の大編成の曲ならばしばしば登場するが、ベートーベンのような泣かせる使い方はそれほど多くない。
例えば、ブラームスの交響曲第1番の冒頭など、重低音がうなりをあげて、弾いている方はなかなかいい気分に浸れるのだが、じつは他の楽器も全力で音を出しており、低音のCといえばティンパニの方が目立ってしまう。ベースは、全合奏の威力を増幅し、下から支えるという「本来の」役目に徹しているのだ。
近代でこの音ならではの使い方をしている場面は、たとえばリヒャルト・シュトラウスの「ツァラトゥストラはかく語りき」の例のC−G−Cの主題などがあげられる。序奏では大太鼓やオルガンが一緒なのでベースは埋もれてしまっているが、「知識について」のフーガの冒頭など、この音がなければ始まらない。ppではあっても、非常によく聞こえるはずだ。
しかし、これだけ重要な低音が、じつは標準の楽器では演奏できないというのも悲しい話である。通常の4弦バスでは、一番低い音がE。アマチュア演奏家の多くは、運命の2楽章で、ああここで本当は宇宙が感じられるはず−−と思いながら、泣く泣く1オクターブ高いCを、精一杯大きな音で鳴らすのだ。
ベートーベンの時代にはコントラCが出せる楽器はおろか、一般にはもっと音域のせまい三弦のベースが使われていたというのに、どの作曲家もこの音を普通に用いているというのは不思議な話である。音楽的にどうしても必要なので、将来の楽器の進歩を期待して楽譜に書き込んでいたのだろうか。これに合わせて標準の楽器がC音を出せるようになっていれば、アマチュアも今のように悲しい思いをせずに済んだはずなのだが・・・
- 当時の楽器は様々な調弦のものがあったので、ベートーベンはコントラCを実際に期待することができたという説もあります。
- 不思議なことに、同じパターンが2回目に登場する(80小節目)ときは、チェロはオクターブ下がるのに、ベースは2拍目も同じ高さのCのままになっています。
- 古典の奏法として、2拍目は基本的には収めて弾きますから、このコントラC派手に強調するのは上品とは言えません。端正な終止で、しかしよく響かせて、というとろこでしょうか。



